インテリアとは「空間のディテール」を考えること|日本工学院八王子専門学校 テクノロジーカレッジ長 山田 俊之先生にインタビュー!
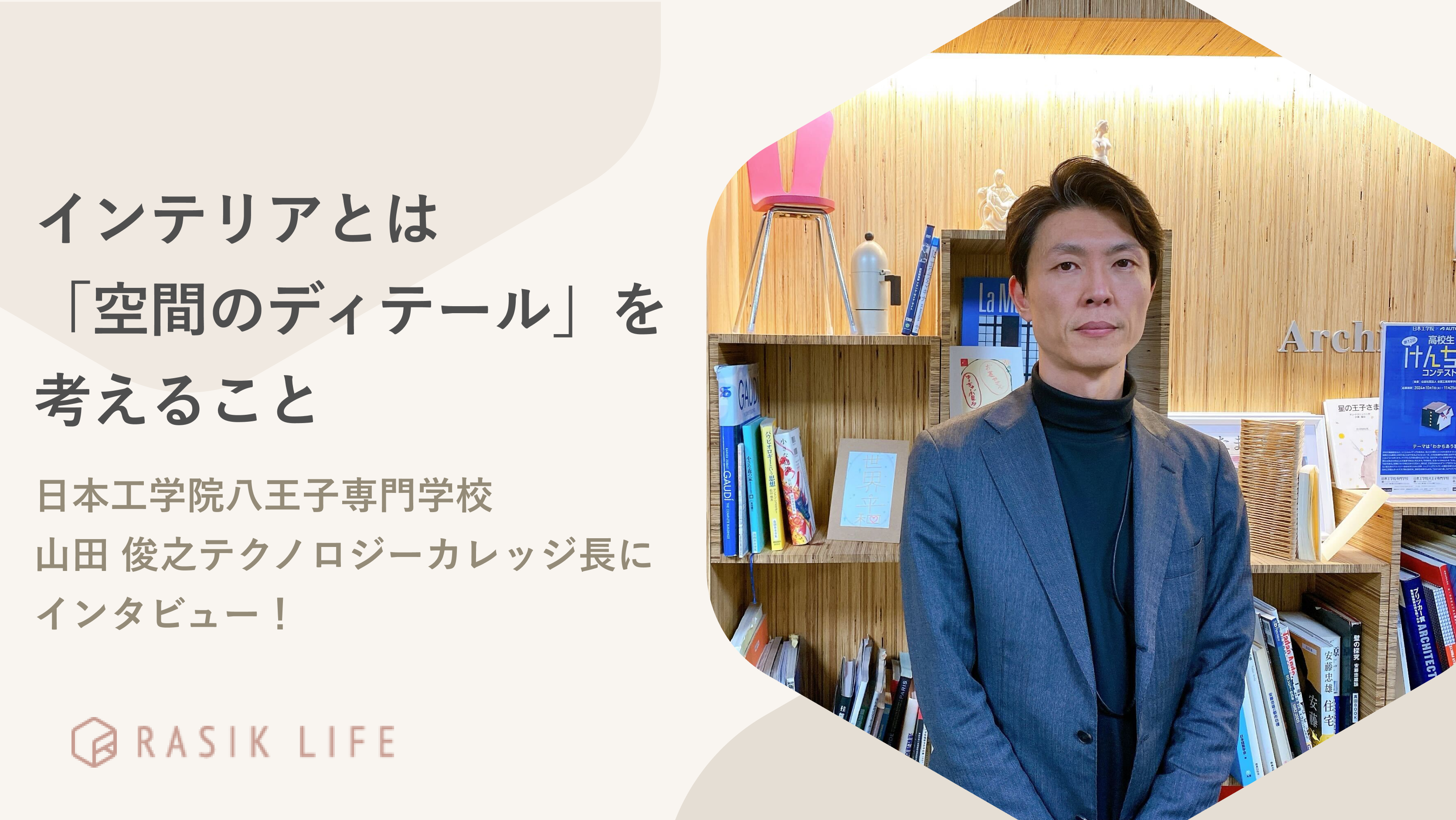
「インテリア」はさまざまな場所で使われる言葉ですが、具体的な意味を知らない人もいますよね。なんとなく「家具」を指す言葉だと考えている人もいるかもしれません。
今回は書籍「初学者の建築講座 建築インテリア」を執筆し、学校では「建築・インテリア入門」の授業を担当されている、日本工学院八王子専門学校 テクノロジーカレッジ長の山田 俊之(やまだ としゆき)先生にお話を伺いました。

2023年にRASIKを運営する株式会社もしもへ入社後、『RASIK LIFE』編集長に就任。自身が持つ不眠症の悩みをきっかけに、寝具について学ぶ。睡眠検定3級。商品の企画・生産・品質管理・販売までを一貫しておこなっている会社の特徴を活かし、実際に商品をチェックしながら記事を作成。フォロワー数50万人超えのRASIK公式インスタグラムでは、商品のレイアウトなども公開中。
公式:インスタグラム
生徒の成長に「教育の面白さ」を感じて教員の道へ

―本日はよろしくお願いいたします。まずは、建築に興味を持たれたきっかけを教えてください。
山田 俊之さん(以下、山田):小学校のころに4回ほど転校し、さまざまな間取りの家に住むなかで建築に興味を持ちました。引っ越すたびに、部屋を家族の誰がどう使うか、家具はどう置けばいいかを家族でワイワイしながら考えていましたね。
幼少期から美術が好きだったこともあり、大学は建築学科のある東京理科大学へ進学しました。研究室の先生は寸法計画を研究されていて「家具の高さは人間の身体寸法をもとに決められている」という話が印象的でよく覚えています。
大学院を修了後は設計事務所に8年勤務し、祖母のマンションのリフォームをはじめさまざまな建物の設計を担当しました。また、そのかたわらで建築士の予備校の講師としても働いていたんです。自分の生徒が1級建築士や2級建築士の資格を取って社会で成長していく姿に教育の面白さを感じたのが、専門学校教員の仕事を考えるきっかけになりました。
日本工学院八王子専門学校からは12年前に声をかけていただき、以降は教員としてずっと働いています。今年からは「テクノロジーカレッジ長」という工学部系の学部を管理する立場として教育に携わっています。
建築の基幹科目には、施主さんからの要望を読み取ってまとめる「設計」と、まとめた内容を図面にして材料を決める「製図」をまとめた「設計製図」というものがあります。テクノロジーカレッジにある建築設計科や機械設計科では、設計と製図という2つの内容は少しバランスが異なります。
機械設計はデザインをどう実物にするか原寸大を基準に考えるのに対して、建築設計は使い勝手を100分の1などの縮尺上で間取りにして考えていく。そういう意味で、機械設計は製図の比重が高く、建築設計は設計の比重が高いと考えています。
インテリアと建築の境目

―インテリアと建築の違いはどこにあるのでしょうか?
山田:もともとは建築とインテリアは同じ分野でしたが、仕事の分業化をきっかけに学問体系も別れていきました。
たとえば、「平面計画」は建築とインテリア共通の工程ですが、建築の平面計画が縮尺1/50程度で考えるのに対して、インテリアでは家具の素材感や納まり方などを想定して原寸で空間をつくる際のディテールまで考えます。家具が空間にフィットするようデザインすることが、インテリアデザイナーの仕事といえるのではないでしょうか。
以前、八王子みなみ野にある学生寮近くのコンビニをカフェに改装する課題で学生に空間コンセプトや空間演出を提案する課題があったのですが、掘りごたつを置いて目線を操作する座敷形式のカフェを提案した案を見た際は「まさに建築とインテリアの融合だ」と感じました。
学科選びに悩んだらやりたいことの解像度を上げる

―建築とインテリアどちらを学ぶか迷った際は、どのように判断すればいいのでしょうか?
山田:建築系の学科では建築士の受験資格を取得できるため、将来的に建物の外側と内側の両方を仕事にできます。一方でインテリア系の学科では、建物の外側について概論として学びつつも、テーブルコーディネートまでを仕事の範囲にすることができます。それを理解してもらいながら、将来的になりたい職業を見据えてどちらを選ぶか確認してもらっています。
もちろん、建築士でなくてもインテリアデザイナーだからこそ考えられる専門領域もあります。たとえばテーブルの飾り付けのためにテーブルクロスの厚みや色味を選ぶ作業は、布に関する造詣が深いインテリアデザイナーの領域ですよね。
建築系学科では建物の全体計画から細部までを考えられるのが特徴で、インテリア系学科は建築の「ソフト」な面を含めて内装を考えられるのが特徴だと考えています。
ただ、最近はインテリアデザイナーが新築の設計を考えることもありますし、建築家がボールペンをデザインすることもあります。そのような意味で、領域がボーダレスになりつつあります。学生自身の将来やりたいことの解像度が上がると、学科を選びやすくなると思います。
知識を理解するために実践する

―授業ではどのような教え方を意識されていますか?
山田:先ほど申し上げたように、建築は「ソフト」と「ハード」の2つの側面がありますが、それぞれで課題を変えるようにしています。
建築のソフトな側面を教える際は、たとえばカフェの内装をどうするかという課題を出すときに、店舗のコンセプトから平面計画が想像できるよう提案するよう指導します。椅子は何席必要なのか、ゆったりできる椅子の配置計画や色、素材などを考えてもらいます。一方でハードな側面を教える際は、給排水設備の配置計画や作り付けカウンターが構造的に持つか、など機能的な視点で指導し、飲食店としてのサービス内容が実現可能なように、クライアント・店主・オーナーの立場から考えてもらうことが目的です。
また、授業は実習系と講義系の2種類に分けることができます。設計製図をはじめとした実習系は、生徒たちが知識をアウトプットして体感的に身に着けていきますが、法規・や色味や素材などを学ぶ講義系は、インプットが多く学生が受け身になりがちな授業です。
私は知識は使わなければ理解しづらいと考えているので、講義系はより授業内容を工夫するようにしています。たとえば、授業の教科書として執筆した「初学者の建築講座 建築インテリア」には各章の最後にワーク問題を入れ、実習系の授業のように得た知識をアウトプットする「実践する作業」を盛り込みました。
値段の高い家具が持つ「安心感」

―インテリア選びでこだわっている点はありますか?
山田:家具選びでは特に素材にこだわっています。触感やにおい、見た目にも影響する要素ですからね。以前からソファの購入を検討しているのですが、肌触りのよさや素材が持つ香りを考慮して、無垢の木材で作られた商品を探しています。
また、価格と品質のバランスもこだわりたい要素のひとつです。私の場合、安い製品を買うとつい手放すときのことを考えてしまいます。廃棄物がどこへ行くのかを考えると、SDGsの視点からも長く使えるいいものが欲しくなりますね。
日本の家具業界は値段が高めの傾向にありますが、それは品質の高さや充実したサポート体制の裏付けだと考えています。私自身、値段の高さから生まれる安心感を根拠に家具を選んでいるかもしれません。ただし、高すぎるものは手が出しづらいので、そのバランスの折り合いをつけるための時間がかかってしまうのが悩みですね。
RASIK LIFEの記事がお客さんの信頼につながっている

―RASIKの公式ストアを見た印象はいかがでしたか?
山田:私は店舗で商品を見たうえで買う人間なのですが、以前に娘の学習机をネットで購入したことがあります。そのきっかけとなったのが、商品ページに書かれていた丁寧な商品説明でした。
ネットで家具を購入するお客さんは、同じ価格帯でも構造や耐久性など商品の特徴を詳しく知りたいのではないでしょうか。またネットストア専売の家具は、店舗で実物を確認できないため品質への不安感を抱きがちだと思います。
その点、「RASIK LIFE」の解説記事はお客さんの信頼度を高めるきっかけになっていると思います。匂いに関する詳細記事やファブリック生地について詳しく解説している記事も、お客さんの視野を広げるきっかけになっているのではないでしょうか。
失敗を恐れていては挑戦できない

―最後に、授業で大切にされていることや学生へのメッセージがあればお願いします。
山田:仕事で信頼されるには、自分の発言に責任を持たなければいけません。授業では、自分の設計に対する指摘にすぐさま返答できるまで深く考えてほしいと話しています。
当然、最初はそこまで考えられない学生もいます。しかし、そのまま卒業して欲しくないので、課題のハードルを下げるとともに、とにかく上手くいったことは褒めるようにしています。結果として、壁にぶつかりながらでも悩んでいた学生が無事に就職できたときは、本当に嬉しく思いますね。
また、成功体験は必要ですが、一方で学生は失敗を恐れがちです。失敗を恐れる人は挑戦できません。講評を受けて「悪い評価を受けた」と落ち込む学生もいますが、講評されたこと自体がプラスになるといつも伝えています。誰からも何も触れられずに終わるほうが悲しいことだと気づかせないと、社会に出たときにとても辛いですからね。
建築設計の考え方は、さまざまな業界で活用できます。たとえばITには「システムアーキテクチャ」という建築にちなんだ言葉が使われていますよね。建築設計は使う相手、住む相手を考えながらおこなう創造的な営みです。建築やインテリアを勉強して相手のことを考える力を身に着けられれば、その人はどこでもきっといい仕事ができると思います。
学生には「建築やインテリアが好き」という気持ちを持って、私たちと一緒に勉強を楽しんでほしいなと思います。
―素敵なメッセージをありがとうございます。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。
【日本工学院八王子専門学校 建築学科 山田 俊之先生】
一級建築士、福祉住環境コーディネーター。東京理科大学 理工学研究科建築学専攻修了(修士)。
主な著書に「初学者の建築講座 建築インテリア(市ヶ谷出版社)」。
日本工学院八王子専門学校では「建築・インテリア入門」「設計製図」「建築法規」などを担当し、現在はテクノロジーカレッジ カレッジ長を務める。
















































