木材を活かした温かな空間づくり|ICSカレッジオブアーツ インテリアデコレーション科 佐々木 高之先生にインタビュー!
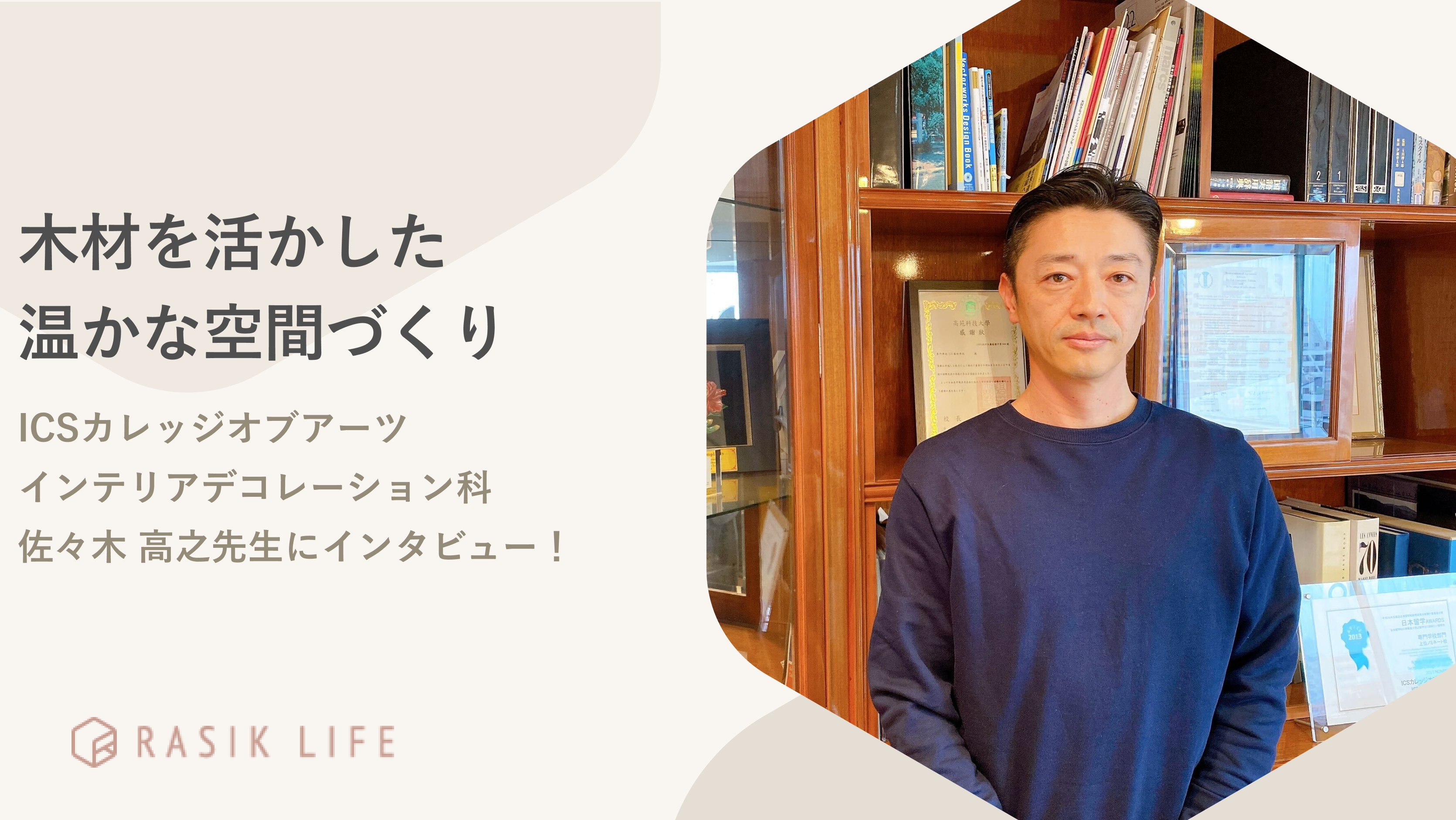
温かみのある空間を作りたいと考えていても、どのようなポイントを意識してインテリアを選べばいいか分からない人もいるでしょう。優しく柔和な部屋づくりを目指すなかで、部屋のカラーコーディネートに悩んでいる人もいるかもしれません。
今回は、専門学校の講師を務めながら、木製のインテリアアイテム「モクタンカン」の販売にも取り組まれている、ICSカレッジオブアーツの佐々木 高之(ささき たかゆき)先生にお話を伺いました。

2023年にRASIKを運営する株式会社もしもへ入社後、『RASIK LIFE』編集長に就任。自身が持つ不眠症の悩みをきっかけに、寝具について学ぶ。睡眠検定3級。商品の企画・生産・品質管理・販売までを一貫しておこなっている会社の特徴を活かし、実際に商品をチェックしながら記事を作成。フォロワー数50万人超えのRASIK公式インスタグラムでは、商品のレイアウトなども公開中。
公式:インスタグラム
大学時代の同級生3人で建築設計に取り組む

―本日はよろしくお願いいたします。まずは、建築設計に興味を持ったきっかけを教えてください。
佐々木 高之さん(以下、佐々木):大学1年のころ、建築学科の先輩から建築家について詳しく聞き、工学的な知識とデザインの両方を活かせる仕事内容に強く惹かれたことが、建築業界を目指すきっかけです。
私は現在、妻の佐々木珠穂(ささき たまほ)、そして荒木源希(あらき もとき)と大学時代の同級生3人で建築士事務所「アラキ+ササキアーキテクツ」を運営しています。
私自身はイーストロンドン大学院を修了し、建築事務所での修行を経て、妻とふたりで独立しました。その際に、同じタイミングで同級生の荒木が独立した話を聞き、荒木を交えた3人でコンペに挑戦してみることにしたんです。結果、いい雰囲気で仕事をすることができ、今の「アラキ+ササキアーキテクツ」の形ができあがりました。学生時代は「3人で仕事をしよう」といった話しはしていなかったので、不思議な縁を感じていますね。
私たちはそれぞれの得意分野や興味の方向性が少しずつ異なっているのが特徴です。役割を分担し、お互いの長所を活かした設計が「アラキ+ササキアーキテクツ」の強みですね。
色味にこだわった温かみのある空間づくり

―住宅設計においてこだわっていることはありますか?
佐々木:大学4年生のころ、当時の建築業界で主流だったつや消しの白い塗装による抽象的な空間づくりに違和感を覚え、以降は真っ白な空間づくりは避けるようにしています。
白色で構成された空間は冷たい印象を与えること、床や壁、天井が派手な色味や白一色だと、心理的な重みが生まれてしまうと考えているんです。住宅設計では、ベージュの塗料や木材を使った、柔らかで優しい空間づくりを意識していますね。
柔らかで優しい家を目指すなかで生まれた「モクタンカン」

―佐々木さんたちが手がける「モクタンカン」について教えてください。
佐々木:仮設足場で使われる鉄製の「単管(たんかん)」という資材を木で置き換えた「モクタンカン」は、もともとリノベーションプロジェクトのアイデアのひとつでした。プロジェクトの終了後、単品でインテリア用品として販売できるのではないかと「モクタンカン株式会社」を設立し、現在は住宅インテリアやイベントスペースの設営で利用されています。
私たちの建築士事務所は、手を使って物事を考える「ハンズオンアプローチ」の手法をモットーにしており、模型製作や試作を目的とした自前の工場(こうば)を持っていたのも、会社を設立したきっかけのひとつですね。
「アラキ+ササキアーキテクツ」の特徴である柔らかく優しい空間を作るには、木の素材感や触感が大切だと考えています。木材を意匠的に取り入れる意識が、モクタンカンというプロダクトの開発にもつながったと思います。
写真からお施主さんの要望を汲み取る

―設計時、お施主さんとのやり取りで大切にしていることはありますか?
佐々木:近年の打ち合わせでは、「こういった雰囲気の家がいい」と、実在する建築物の写真やSNS画像を見せながら説明してくれるお施主さんが多いです。
しかし、私たち建築士とお施主さんでは建築写真に対する目線が異なるため、重視するポイントがズレてしまうことがあります。そのため、お施主さんが写真のどんな要素を気に入っているのかを細分化して丁寧にヒアリングしなければいけません。
たとえば、有名な建築作品が好きだと写真を共有された際は、建築物の構造を評価しているのか、単に壁のデザインが好きなのかなど、お施主さんが意識しているポイントを話し合いを通して探るようにしています。
ICSカレッジオブアーツの「即戦力」を意識したカリキュラム

―ICSカレッジオブアーツでは、どのような授業を担当していますか?
佐々木:私はインテリアデコレーション科で「デザインチュートリアル」という授業を担当しています。学生が制作したデザイン課題に対し、実際の建築士事務所と同じように打ち合わせをおこない、アドバイスをする授業です。ただし、授業の場合、私のデザインではなく、あくまで学生本人のデザインなので、学生へのアドバイスに徹するよう意識していますね。
また、週に1回の「基礎講座」「実践講座」では、知り合いのデザイナーをゲストとして招待し、レクチャー形式の講義を実施しています。
こうした実践的なカリキュラムがICSカレッジオブアーツの特徴で、卒業後に「即戦力」として働けるスキルを身につけることができます。実際に「モクタンカン株式会社」では、当校の卒業生が製作やデザイン、販売を担当しています。
RASIKのショップからは「目新しさ」を感じた

―RASIKの第一印象を教えてください。
佐々木:ベッドを中心とした通販サイトはあまり見たことがなかったので、今までにない新しいタイプのインテリアショップだと感じました。
現在もさまざまな種類のベッドが販売されていますが、よりデザインのバリエーションが広がっていくと、お客さんも嬉しいのではないでしょうか。
「デザイン」は使う人の立場から考える

―最後に、建築・インテリア業界を目指す人へのメッセージをお願いします。
佐々木:私は学校で、よくアートとデザインの違いについて話しています。
アートは制作物を通して自己表現をし、受けた人にさまざまな捉え方をしてもらうものです。対してデザインは、自己表現ではなくて他者を表現する仕事です。デザインにおいて最も大切なことは、その建築を使う人にどう思ってもらえるかだと私は考えています。
建築・インテリア業界問わず、デザイナーを目指す人は自己満足せずに使う人の気持ちや立場をふまえたデザインを心がけてほしいですね。
―素敵なメッセージをありがとうございます。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。
【ICSカレッジオブアーツ インテリアデコレーション科 科長 佐々木 高之】
二級建築士。1978年広島県生まれ。2002年東京都立大学工学部建築学科卒業。2005年イーストロンドン大学大学院修士課程修了。2005年〜2007年NAP建築設計事務所勤務。2008年アラキ+ササキアーキテクツ設立。2012年スペースデザインコンテスト1位、2013年住宅建築賞、東京建築賞戸建住宅部門最優秀賞、2014年グッドデザイン賞、リノベーション・オブ・ザ・イヤー総合グランプリなど受賞多数。
2009年よりICSカレッジオブアーツにて講師を務め、現在は科長。担当授業は「デザインチュートリアル」など。
















































