建築家として「住まいを持つ幸せ」を届けたい|福山大学 工学部 建築学科 河口 佳介教授にインタビュー!
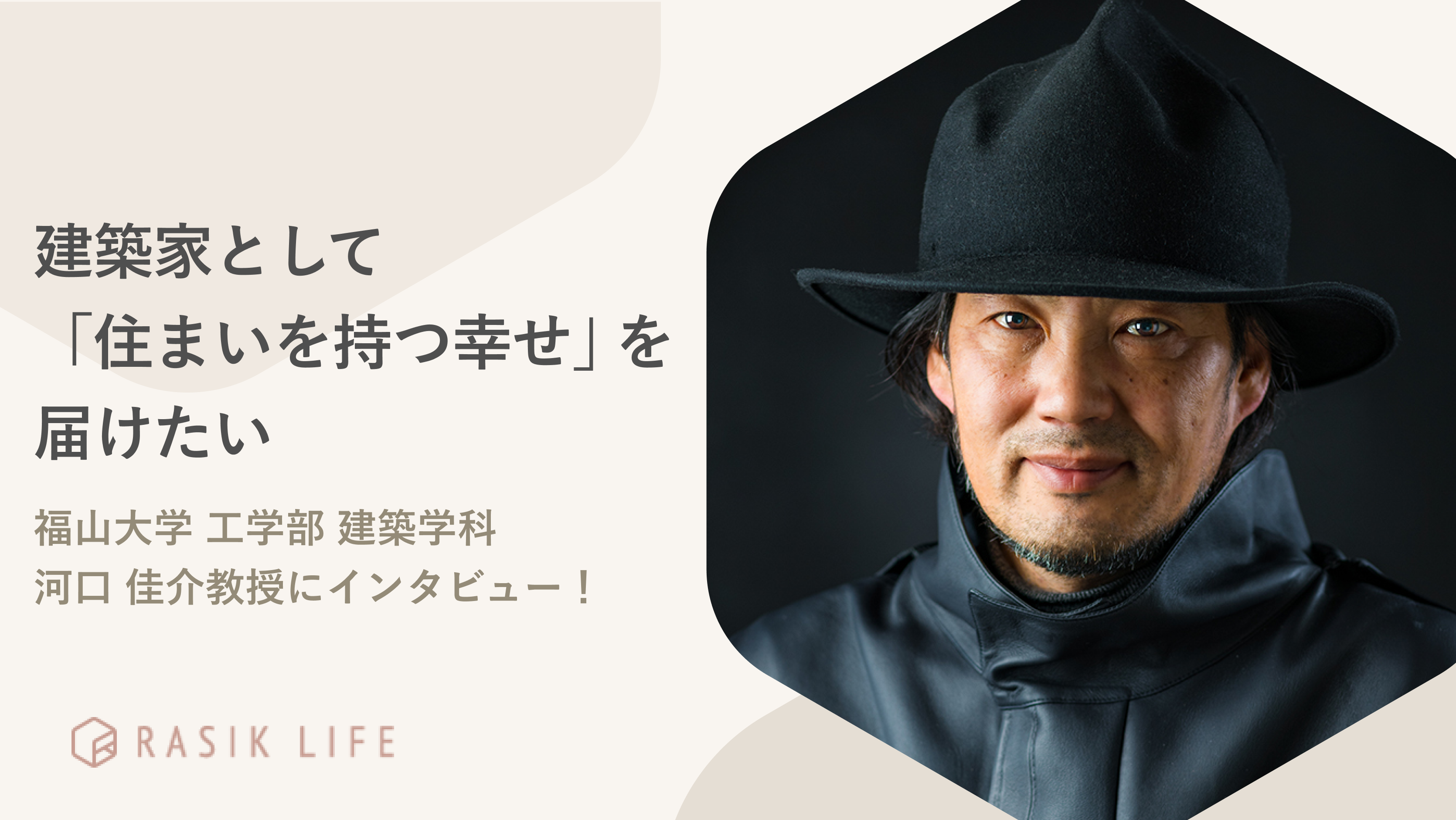
住まいづくりを考える際、なにを優先するべきかわからなくて悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
今回は、自然環境と住む人の生活を尊重した設計をおこなう建築家であり、大学で教授も務められている福山大学 工学部 建築学科の河口 佳介(かわぐち けいすけ)教授にお話を伺いました。

2023年にRASIKを運営する株式会社もしもへ入社後、『RASIK LIFE』編集長に就任。自身が持つ不眠症の悩みをきっかけに、寝具について学ぶ。睡眠検定3級。商品の企画・生産・品質管理・販売までを一貫しておこなっている会社の特徴を活かし、実際に商品をチェックしながら記事を作成。フォロワー数50万人超えのRASIK公式インスタグラムでは、商品のレイアウトなども公開中。
公式:インスタグラム
住まいを持つ幸せを届けたくて独立した

―本日はよろしくお願いいたします。まずは、住宅設計に興味を持たれたきっかけを教えてください。
河口 佳介さん(以下、河口):私は40歳前後まで広島県福山市で暮らし、地元の小さなゼネコンで働きながら設計を学びました。
しかし、働いていた会社には15人前後の上司がいたので、自分がやりたかった意匠図の仕事を担当できない日々が続きました。7、8年経っても意匠図の仕事が回ってこないので、頭にきて会社を辞めてしまったんです(笑)。
当時の会社では上司に建築を教わることはありませんでしたが、資格を取っておかないと建築家になれないと考えていたので、自分で勉強して25歳のときに一級建築士や一級施工管理技士の資格を取りました。ただ、「準備万端だ」と思って会社を辞めたのですが、独立した当時はバブルが崩壊したタイミングで、右を向いても左を向いても仕事が見つかりませんでしたね。
大手の建築事務所から仕事をもらえるような実力もなかったので、小さいことをコツコツと積み上げていくべきだと考え、どんな仕事でもこなしました。足場屋さんで足場を組むこともありましたし、皿洗いのアルバイトもしました。建築家になるための鍛錬の場だと思って、本当になんでもやりましたね。
その後は少しずつ建築の仕事が増えて、福山市の小さな住宅の設計を手がけるようになったのですが、そのときに「お金がない人に住宅を持ってほしい、自分の職能で住宅を提供したい」と考えたのが建築家としての原点です。アパートに住んでいる人に「人生の豊かさや、住まいを持つ幸せを届けたい」という思いが、住宅設計をやろうと思ったきっかけですね。
スタッフと一緒にコンクリートを打設した「瀬戸内の家」

―ご自宅である「瀬戸内の家」を建てる際のエピソードを聞かせてください。
河口:「瀬戸内の家」は37歳ぐらいのときに作った実験住宅です。設計事務所として独立したものの仕事も少なかった時代なので、土地をなんとか安く購入して「さあ建てよう」と思ったときには残り2,000万円程度しか手元にお金がなかったんです。
そこで、コストを抑えるためにさまざまなことに挑戦しました。中間業者が入らない「コンストラクション・マネジメント」と呼ばれる分離型の発注作業を進めたり、建物の平面を単純化させることでガラス面を増やしたりしました。山の上にある土地で眺めがよく、さらに国立公園に囲まれた立地だったので「窓から切り取れる風景は全部自分の庭だ」ぐらいの気持ちで設計をしていましたね。
ただ、工夫して費用を抑えてはいましたが、お金がないことには変わりはないんです。予算2,000万円で「RC造りのガラス張り」という東京では考えられないようなアプローチでしたが、やりきろうという気持ちは持ち続けていました。
実は、1階のコンクリート部分は建築事務所のスタッフと一緒に打設したんです。打設作業の前日、「明日は合羽を持って現場の最寄り駅に集まってね」と伝えたら、スタッフはハテナマークを出していましたね(笑)。女の子のスタッフも来てくれて、セメントだらけの顔になりながら夕方まで一緒に作業してくれました。
型枠も、大工さんが組んでくれたんですよ。タイル屋さんも「これ使っていいぞ」と資材を分けてくれました。みなさん「河口がすごいことをやりはじめたな」と、期待してくれていたのだと思います。
さまざまな方の協力もあってなんとかできあがったのが「瀬戸内の家」です。でも、それらの経験を自分がしたことで、「これくらいでガラス張りができるんだ」といった建築の原価がわかるようになりましたね。今だったら絶対2,000万では作れないと思います。破格値で作り上げたというのも、あの家が持つエピソードのひとつです。
自然と一体に暮らせる豊かさを知ってほしい

―「瀬戸内の家」を建てようと思ったきっかけはなんですか?
河口:以前、「河口さんの設計する家と、ハウスメーカーの家はどちらがいいですか?」と聞かれたことがあるんです。
そのときに「この人たちは豊かさを知らないまま、私に声をかけてきているんだな」と感じたんです。まずは「豊かさ」というものを知ってもらわないといけない、建築家として見本となるような自分の家を建てて世間に知らしめなきゃいけないんだと考えましたね。人々に豊かさとはどういうものかを教えたくて「瀬戸内の家」を設計したんです。
学区がいいとか、コンビニが近くにあるとか、新幹線が近くで止まるとか、利便性は関係ありません。自然と一体になって暮らせる環境だったり、それを自分の庭のように思える景色がもたらすものを伝えたかったんです。
子ども時代の記憶がきっかけで生まれた「大山のゲストハウス」

―「大山のゲストハウス」を設計するきっかけを教えてください。
河口:「瀬戸内の家」が小学館の『プラチナサライ』という雑誌の表紙に掲載されることになったのがきっかけです。ちなみに、前号の表紙は当時アメリカの大統領だったバラク・オバマさんで、次号の表紙は黒木メイサさんでした。周囲に「彼らと肩を並べたよ」なんて話して「ばかじゃないの」とよくつっこまれていました(笑)。
新聞に自分の名前が載った雑誌広告が掲載された際に、それを見ていたのが新聞社で働いていた「大山のゲストハウス」の施主さんでした。「別荘を建てようと考えているが、河口さんはこれから有名になって忙しくなりそうだから、いまのうちに予約させてほしい」と電話をかけてきてくれたんです。
施主さんからは木々を伐採して別荘を建ててほしいと言われましたが、実際に山中の大木たちを見て、こんなに立派な木を切るのはかわいそうだと思いました。私が子ども時代に山のなかで遊んでいた記憶も影響しているのでしょうね。そこで、木々の合間を縫って建てるというコンセプトを思いついたんです。大山のゲストハウスのサブタイトルが「森の隙間」なのは、そういった経緯があります。
大山のゲストハウスは、『BARBARA CAPPOCHIN 国際ビエンナーレ』という賞の建築部門と環境部門にダブル入選した初めての作品となりましたが、実はグランプリが取れそうだったんです。ふたつの部門にエントリーしたせいでグランプリを逃してしまったらしく、知り合いの審査員から「なぜ1部門だけに絞り込まなかったのか」と言われてしまいました。ですが、ダブル入選というのも私らしいエピソードだなと思っています。
ほかにも「大山のゲストハウス」は、『CASABELLA』という100年以上の歴史を持つ世界で最も古い国際建築雑誌に掲載されたり、中学校の美術の教科書に掲載されたりもしました。学校のテストに自分の名前が出ているかもしれないと思うと、照れくさくて笑ってしまいますね。
これだけの人々に評価してもらえたのは、お金が少ないなかでも自分の夢を叶えるために勇気を持って「瀬戸内の家」を作ったことが大きいと思っています。人に豊かさの原点を理解してもらおうと建てた家が、「大山のゲストハウス」をはじめとした後の作品につながっていきました。
建築家は夢と勇気を持たないといけませんよね。施主さんも、夢のない人には絵を描いてもらいたくないと思っているのかなと考えています。
インテリアはバランス感覚が重要

―インテリアへのこだわりがあれば教えてください。
河口:私は、本物の素材が好きなんです。たとえば木材を使いたいときは、木に似せたコンクリートは使わず、木材を厳選して使います。
本物の素材はゆっくりと年月を重ねてくれるという特徴があります。また、ベースとなる住宅の素材が本物であれば、そこまで高い家具でなくても空間全体を引き立たせることができるんです。キャンバスがいいと絵の具のノリがよくなる感じに近いですね。
また、家具を引き立たせようとするときは、その空間の端のラインをシンプルに構成させることが重要ですね。柱や梁をプラスターボードで囲んで空間をデコボコさせてしまうと、人間の脳が線を数えだして、空間のラインに意識が向いてしまうんです。そうすると、どんなによい家具を置いても認識がぼやけてしまいます。
加えて、家具の色と壁の色の対比も重要です。建築空間は音楽の和音と一緒で、美しく見える色調のコンビネーションがあるんです。たとえば、紫色と黄色と茶色に、組み合わせてもダメだと思える色調に白色を入れてみると、とてもかっこいい空間ができるんです。
ワンランク上のコーディネートを考えるなら、色調のコンビネーションを理解したうえで崩すという選択肢があります。たとえば、モダンな空間にペルシャ絨毯を敷いてみるんです。「本物の質」を理解していれば、そういう風に崩すことができるようになります。
インテリアは、硬いものと柔らかいもののコントラストが大切です。私は、それらをまとめて「素材のコントラスト」と呼んでいます。硬いものと柔らかいものを同じ空間に佇ませることや、さらに色調のハーモニーを加えた総合的なバランス感覚が重要だと思います。
材料を活かすと機能美が生まれる

―RASIKの家具デザインに期待していることはありますか?
河口:材料の良さを活かした家具作りをしてもらえたら嬉しいですね。そうして作られた家具には「その材料ならではの特性」が備わると考えています。機能美とも言えるかもしれません。
たとえばソファなら、材料の特性をふまえた座り心地やデザインになるといいなと思いますね。建築家は、そういった感覚を理解したうえで家を作っています。理論武装が必要な仕事ではありますが、理論で格好をつけても感覚が無ければ通用しないというのが私の考え方なんです。
山頂に大きな旗を立てるような人生を歩んでほしい

―最後に、授業で大切にされていることや学生へのメッセージをお願いします。
河口:「もっと遊んでほしい」というのが正直なところです。建築は、人生観からにじみ出てくる感性で作ってもらいたいなと思っています。そうでなければ人の真似しかできなくなり、建築家としては長続きしません。
ですから、建築科の学生には美味しいものを食べたり旅行に行ったり、若いときじゃないとできないことをするといいよと話していますね。これを勉強しなさいといったことはあまり言わないようにしています。教授としては変わっているかもしれませんね。
「先生ってどういう学生時代を過ごしてたんですか?」なんて聞かれますけど、私は授業を抜け出して、ディスコで踊りまくっているような学生でした(笑)。それでもこうやって大人になれるんです。
一生懸命に勉強したからといって、世間で通用するわけではないんですよね。最近はネットで得た情報だけで人生を生き抜こうとしている人もいますが、3年くらいは自分の力で歩いてみるべきだと思うんです。
私はパソコンの使い方もよくわかっていませんが、それでも人々に必要とされて仕事の話を頂けています。大学でたくさん勉強して優秀な人材になることを目指すより、まずは人に優しくあってほしいです。そして、建築設計を通して、人として徳を積んでもらいたいなと考えています。
社会の一駒で終わるような人生ではなく、「私はここにいる」と大きな旗を立ててほしいなと思いますね。
また、私の事務所の「K2デザイン」という名前は、河口圭介のイニシャルとK2という山のダブルミーニングで、設計業務と登山を掛け合わせて考えました。
K2は、世界で最も登頂するのが難しい山と言われています。登山では8合目までチームで登りますが、山頂に旗を立てるのは、登山家本人なんです。建築も同じことが言えると考えていて、登山家、設計者しか山頂には立てないんですね。
最後は自分で山頂に旗を立ててほしいという思いを込めて「K2デザイン」という社名を付けました。世界で一番高いエベレストではなく、世界で一番登頂するのが難しい山に旗を立てる意味も感じてもらいたいですね。
―素敵なメッセージをありがとうございます。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。
【福山大学 工学部 建築学科 教授 河口 佳介】
一級建築士。K2-DESIGNARCHITECT&ASSOCIATES代表。
代表作に「瀬戸内の家(2009年度グッドデザイン賞、BARBARA CAPPOCHIN 国際ビエンナーレ2011 優秀作品賞)」「FLAT40(2013年度グッドデザイン賞、ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2018 Architecture Single Residence 部門 5スター受賞)」「大山のゲストハウス -森の隙間-(BARBARA CAPPOCHIN 国際ビエンナーレ2013 一般・環境 優秀作品選出)」など。「大山のゲストハウス -森の隙間-」は中学生用の美術の教科書にも掲載されている。
2024年より福山大学工学部建築学科教授に就任、現在は「建築設計演習Ⅱ」「建築設計演習Ⅲ」「建築設計演習Ⅳ」「スタジオ演習」を担当。
















































